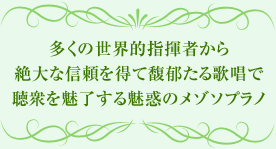二期会ゴールデンコンサート at 津田ホール 2014年1月18日(土)
竹本節子が、東京フィルのコンサートマスター荒井英治、名コレペティトゥアでもある指揮の大島義彰とタッグを組んで創りあげるゴールデンコンサート。 |
 |
二期会ゴールデンコンサート at 津田ホール 日時:2014年1月18日(土) 16:00開演/15:30開場 ●デュパルク 「旅への誘い」 「悲しい歌」 |
《ご予約・お問合せ》 |

竹本:お蔭様で私はこれまで内外の様々なタイプの巨匠といわれる指揮者の方々とも沢山お仕事をさせて頂きました。オーケストラとご一緒する演奏会では、オペラのように毎日毎日練習をしてそこに積み上げてゆくというよりも、本番の何日か前に皆さんで顔合わせして、マエストロ(指揮者)がいらして、オーケストラと合わせます。
私が「たぶんこの曲はこうであろう」と考えていたことではなく、新しい方向で要求が出されてきます。オーケストラもその中でどんどん音色が変わってきて、歌い手もフレージングや声の響きの位置を変えながら、指揮者の求めている音楽に必要な音色やテンポを把握して、その場その場でお互いに創りあげ仕上がってゆくことの醍醐味に捕われてしまったと言えます。そんなわけで、今回このゴールデンコンサートでも、何か通常のピアノで声を聴かせるというリサイタルでないかたちということを模索して、このようなかたちに辿り着きました。
東京フィルのコンサートマスターとして長年活躍なさっている荒井英治さんが、今回の演奏会にメンバーとして加わってくださいます。竹本さんとの出会いについて教えていただけますか
竹本:東京フィルとは、オペラや音楽会で共演していますが、それまで荒井さんとはご一緒したことがなかったんですよ。出会いは、私がかつて(KAY合唱団の演奏会で)バッハの「ロ短調ミサ」を歌った時、コンサートの当日にコンサートマスターの方が急にご都合が悪くなられて、急遽、荒井英治さんがピンチヒッターでコンサートマスターとして、いらしてくださったことがあったのです。そこでヴァイオリンのオブリガートのついたアルトの曲がありまして、それを演奏した時に何か突然、雷に打たれたように感激してしまったんです。私も荒井さんのソロに感激しながら歌って、私が歌う姿に荒井さんも「おもしろい人だなぁ」って思ってくださったみたい。
それから、荒井さんから一緒に音楽をやりませんかとおっしゃっていただいて、「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帖」というグループで荒井さんが指揮をしたり、ヴァイオリンを弾いたり、歌を歌ったり、というコンサートで何度かご一緒したり、東京フィルのトップメンバーによる弦楽四重奏で『カルメン』ハイライトを上演したり、レスピーギの「日没」というような演奏会に出演させて頂くような機会を得たのです。
そこから生まれる音楽は、その時にお互いの息を感じてフォローし合うということや楽譜との取り組み方についても新しい発見があったり、オーケストラの方が持っている音楽性に触発されて、その時々に新しい音楽が生まれてくる。そうした時間に接した経験は私にとって本当に貴重で幸せな時間でした。
ですから、今回、二期会ゴールデンコンサートに出演のお話を頂いた時も、「自分に合わせて頂戴」とピアノの伴奏で私の声を聴かせるというようなリサイタルではなく、竹本節子という歌い手がどうだというのではなく、オーケストラの中で「人間の声」という役をするということを念頭に置いて、時にはオーボエと一緒に、ビオラと一緒に音楽が流れていったり、音楽と重なってゆくような演奏会が出来ないか・・そんな事を考えていて、まっさきに頭に浮かんだのが私の大好きなヴァイオリニスト荒井英治さんだったのです。
竹本さんはじめ出演者の皆さんによるそうしたセッション的なものを今回のリサイタルでは聴けるということですね
竹本:皆がその名手かもしれません。大島義彰さんもピアニストして弾くというより、指揮者として音楽を作ってくださるでしょうから。大島さんは、私が二期会のロッシーニ『チェネレントラ』(シンデレラ)のタイトル・ロールを歌った時にプロンプターをしてくださったのが最初の出会いです。
 |
大阪フィル定期では福井敬さんをはじめ錚々たるメンバーでのサン=サーンス『サムソンとデリラ』を2日連続本番で歌った時にも副指揮として音楽を創りあげ、二期会のメンバー全員の発音、発語を含む音楽指導をなさってくださいました。本当に信頼する指揮者のお一人なんです。 |
1998年2月 東京二期会 |
桐朋学園大学に学ぶ。鈴木共子、江藤俊哉の各氏に師事。ジャンヌ・イスナール、ガブリエル・ブイヨンにもレッスンを受ける。79年から新星日本交響楽団、80年から東京交響楽団、そして89年からは東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスターを歴任し、現在は東京フィルハーモニー交響楽団のソロ・コンサートマスター。92年、モルゴーア・クァルテット結成に参画。ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲全15曲に取り組み注目を浴びる。その後も古典派と現代曲を組み合わせた独自のアプローチを展開、日本を代表する弦楽四重奏団としての地位を得る。98年、第10回「村松賞」、2010年度「アリオン賞」を受賞。2012年にはプログレッシヴ・ロックへのオマ-ジュである【21世紀の精神正常者たち】をリリ-スして話題となる。独奏者としても、J. S. バッハからショスタコーヴィチ、リゲティに至る数多くの協奏曲を秋山和慶、大野和士、ルドルフ・バルシャイ、ヤーノシュ・コヴァーチュ、井上道義等と協演する。また、V. フェドセーエフに招かれ、モスクワにてモスクワ放送交響楽団と共演している。 |
東京藝術大学指揮科卒業。同大学院修了。その後フランス政府給費留学生として渡仏、パリ国立高等音楽院に学ぶ。平成8年度文化庁芸術インターンシップ研修員として奨学金を受ける。フランス外務省助成による、モノオペラ「人間の声」(F・プーランク作曲)をマニラ、ジャカルタ、香港、日本各地にて演奏。オペラ「エトワール」、「教育不行き届き」(E・シャブリエ作曲)、「シブレット」(R・アーン作曲)を指揮する等(すべて日本初演)、フランス音楽のスペシャリストとして特に高い評価を受けている。東京二期会オペラ劇場と長期に渡り専属契約を結び、多くの本公演に際しコレペティトゥア、副指揮者、合唱指揮者として参加し公演の成功に貢献、極めて厚い信頼を歌手たちより受けている。2006年7月びわ湖ホールでの「ミニヨン」50年振り日本上演を指揮。2008年10月の藤沢市民オペラ「メリー・ウイドー」を指揮。現在東京藝術大学講師として後進の指導にあたる他、フリーの指揮者として各オーケストラに客演。ピアノ伴奏者としても多彩な活動を繰り広げている。 |
選曲について フランス歌曲への想いは
竹本:フランス歌曲に関しては、学生時代から将来「大人になったら歌いたいな」と思っていた曲を選びました。音は取れるけれども、歌詞の内容や苦しみだとか悲しみだとか、物事に対する距離感だとか、時間を感じられるようになるには(想像力や)ある程度の年齢を重ねないとわからないものがあるのではないでしょうか。
デュパルク「悲しい歌」、ショ―ソン「リラの花咲く頃」・・。
今にも息が絶えて、もう死んでしまいそうに辛い歌詞なんですが、憧れていました。若い頃には歌ってもそこに入りこめなかったものが、実年齢とともにやっと少しずつ解りかけてきたような気がしています。
フランス歌曲を歌うには、声で振り回しては駄目で、想いを伝えるということが大切だと思います。立派の声で歌えば良いというものではなく、私はこれからは掠れた声とか、はかなく消えてゆく声とか、そこに表現を作ってゆけたらなぁと思います。
私が大きな声を持っていると人はお思いになるんですが、それは逆で、表現のダイナミックの為にピアニッシモというものを自分では鍛錬したつもりです。
竹本さんといえば、たぐい稀な深い音色の艶やかな声をお持ちの演奏家という印象ですが
竹本:持ち声は今も明るい響きです。歳をとってマルチェリーナを歌ってみて、「これがやはり一番私にとって無理しないで歌えるものだ」と再認識しました。
マルチェリーナは『フィガロの結婚』の中で、喜劇的なキャラクターと大人の女であるとてもシリアスな部分を演じ分けます。私は楽譜の中からお芝居を見つけ、相手役にその都度反応して舞台を作ることが大好きです。
日本人のメゾやアルトというのはとても人数が少ないんですよね。私は低い音に関してはとても苦労しました。
でもこれまで、やはり若さもあるし、いろいろな音楽に触れてゆきたくて、アルトと言われるマーラーの作品にも挑戦し、その音色を作るために声帯の位置とか伸ばし方とかいろいろ研究して、耳鼻科の先生からは、「5年、10年経つうちに声帯が変化してきましたね。」と言っていただきました。声帯周囲の筋肉が発達したのだと思います。
そして今、マーラー2番、3番、8番、「大地の歌」は、私にとってとても大切な曲となりました。
 |
2006年9月 |
プロとして声を作りあげるということ |
竹本:ずっと順風満々な歌手生活を送ってきたわけではありません。低い音から高い音まで出せるようになったのは、怪我をした後ですね。
頑張ろうとしても力が入らず、何も頑張れなかった時、「歌う」ということだけに身体が反応して、出来るようになった。きっと身体の使い方が変わってきたんでしょうね。
歌い手って言うのは、「声を鍛える」「楽器を作る」と共に年齢によってどんどんロール(役柄)が変わってくるので、その変わってゆかなければならないところを自分で慎重にやってきたということですね。たとえばヴェルディのクイックリー夫人やレクイエムはレパートリー中のレパートリーですが「敵役のような力強い声の役は私はやらない!」って決めて一切手を出さなかったです。
竹本さんはオーケストラ伴奏で歌曲を沢山歌われていますね。
若杉弘指揮で歌われたワーグナーの「ヴェーゼンドンク歌曲集」等も素晴らしかったのを記憶しています。そして竹本さんはこれまで、沢山の巨匠たちと共演していますが、特に印象に残るエピソードを教えてください
竹本:そうですね。オーケストラとともに歌曲を歌えるという経験は珍しいかもしれません。
都響でのガリー・ベルティーニ氏がおっしゃった「歌曲も表現の中に女優でなければならない。ピアニッシモを武器にせよ。」という言葉がその後の私の演奏に大きな影響を与えたし、支配したかもしれません。
若杉先生はバッハ「マタイ受難曲」の練習を柿の木坂のご自宅で、本当に何日がかりで指導してくださったのが思い出されます。ご自身の想いを伝えようと。「ヴェーゼンドンク」の時はすごく思い入れがおありでしたね。
ベルティーニ先生との出会いによって、表現者としてどうあるべきかということや、ピアニッシモを鍛え抜かれたということですね。
では、朝比奈隆先生との出会いについては?
竹本:朝比奈隆先生は、戦後の時代にオペラの日本語訳を逐一付けていった方ですから、歌い手に対する愛情はとても大きかった。マーラーの「復活」の第4楽章にしても本当思い入れが強かったです。彼は音楽を上海で勉強しているのです。なぜなら多くのヨーロッパ系やロシア系の亡命ユダヤ人のトップアーティストが当時、上海に集まってきていたんです。
彼は進駐軍のようなかたちで上海に行っていた占領側の人間であったけれど、ドイツ系の音楽を上海にいるユダヤ系の人たちに教えて貰ったとおっしゃっていました。
それでドイツものに関してはものすごく尊敬と愛情が深かったのです。
最初にフォアジンゲン(指揮者への声聴き)で歌ったのがワーグナー『ラインの黄金』のエルダだったのですけれど、彼は「じゃあ、私が今からオーケストラをするから歌ってみなさい」と言って、ピアノの位置を変え、指揮台の位置を変え、一時間半くらいものレッスンがはじまったのです。
いくつか曲を用意していったのですが、それは聴いてはいただけず、歌った後に(私は神戸出身なんですが)「うちからこんなのが出てきたかぁ」と、神戸にお住まいの先生は、愛情深くおっしゃってくださいました。
それがきっかけでマーラー「復活」に出演することになり、以後も多くのコンサートに出演させて頂きました。
日本の音楽界を創りあげてきた素晴らしい巨匠たちとの関わり・・
贅沢な時代でしたね
竹本:私は自分自身は「人間の声」という楽器としてオーケストラの中で、どうお役に立つのかといつも考えていますから、「私がこう歌います」というような姿勢をとったことはこれまで一度もないです。たぶん、どんなソリストが右と左にいらしてもその時の声色やテンポ感を察知してそこに合わせ入ってゆく自分を楽しんでいます。
まさにプロフェッショナルの極みですね。今回のゴールデンコンサートが益々楽しみになって参りました。最後にゴールデンコンサートにいらっしゃるお客様にもう一言メッセージをいただけますか
竹本:荒井さんが、今回は私の全く知らない曲の楽譜を持ってきてくださいました。ラフ「インマー・バイ・ディア(Immer bei dir いつもあなたの傍に)」などもそうした提案を受けてプログラムに加えたものです。20代の頃にはただ声を振り回して、ただ楽譜をなぞっているだけの演奏をしていたこともあったと思います。年齢とともに言葉への感性、音楽への感性、感じ方が変わります。ピアノとかピアニッシモという記号に対しての思い入れが変わってきました。
オーケストラの中ではアルトやメゾソプラノは、悲しみ、慈悲、人間の嘆きなどを担当します。他のパートにはない感情表現を今の私とすてきな共演者の方々とで紡ぎだせればと思います。私たちの音楽をお楽しみ頂ければ幸いです。
2013年11月10日 ヴァチカン国際音楽祭にソリストとして出演 |

 インタビュー
インタビュー